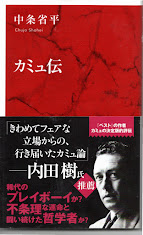はじめに
私が大学生であった頃、大学生活は、人生の半分に相当すると自分に言い聞かせながら生きていた。そしてその後60年生きてきて、全くそのとおりだったと近頃感じている。その理由は、あの当時感じていた、課題や問題意識が60年たってもやはりあまり変わらないと思われるからだ。つまり、80歳を超えてからの日々が、あの当時の課題や問題意識の延長上にあるように思われるせいだ。カミュ(1913~1960)をめぐる問題もその一つだ。
私がカミュの名前をしったのは、大学1年生の時に、同級生のS君と知り合いになったことに関係している。一浪して入ってきた彼は、私より1歳年上であったが少し変わっていた。田舎出の私は、安保闘争後の余波に揺れる大学生活の中で、瞬く間に学生運動の波に巻き込まれていったが、そうした騒然たる流れの中の片隅で、彼は1人冷ややかな目でしかし少し去りがたい面持ちで、孤立して生きているようであった。
その彼と話しをするようになったのは、イギリスの作家ゴールズワージーの「林檎の樹」をテキストに英語の梅津先生の講義に触発されたことがきっかけであった。我々二人は、梅津先生の作品を通して語る人間観に、大きな影響を受けたのだった。その梅津先生は、イギリスの銅板画家で詩人のウイリアムブレイクの研究者だった。その先生の講義が終わったとき、彼が、梅津先生の家を訪問して、もっと話を聞こうと提案し、二人で希望ケ丘の先生の自宅を訪ねたことがあった。当時先生は、奥さんと小学生の女のお子さん二人との4人暮らしであったが、突然の学生の訪問にも嫌な顔をせず、自宅に招き入れてくれた。二階建ての住宅の中二階の三畳ばかりの小部屋が先生の書斎で、そこで先生は、現在自分が行っているウイリアムブレイク研究の現状や出版予定について話をしてくれた。この出来事があってからか、彼とは文学や異性について話をする間柄になった。
その彼が、ベレー帽をかぶり、パイプ煙草をくゆらせて、大学構内を闊歩するようになったのは、それから間もなくのことであったが、その彼が抱えていたのがカミュの「シーシュポス(ジュンボス)の神話」であった。カミュがサルトルと並ぶフランスの実存主義的ニヒリズムの作家であることは、なんとなく知っていたが、当時の私には、実存主義やニヒリズムにはあまり関心がなかった。しかし、米ソの冷戦体制下で、核戦争の危機が切迫していた時代の雰囲気の中で、そのニヒルな感覚は手に取るように感じていた。そしてそのニヒルな感覚は、S君だけで十分であり、私の関心はカミュには向かわなかった。
その私が、カミュの名前とS君を思い出したのは、コロナ下で、岐阜の女性の知人からカミュの「ペスト」を読んだと知らされ、その感想を求められたからであった。そしてその時、私は、カミュの作品をほとんど読んだことがないことに気づかされた。その記憶が潜在意識の中に残っていたためであろう。今年2025年の3月古書店の一角で、カミュ伝と云う本に出合った時、反射的に購入することになった。それが次の本であった。
「カミュ伝:中条省平:インターナショナル新書:集英社:2021年8月11日第一刷発行」
カミュ伝について
「「異邦人」「ペスト」と云う世界文学史上燦然と輝く傑作を発表し、ノーベル文学賞を受賞。かずかずの栄光に包まれながら、自動車交通事故により突如この世を去った不世出の作家アルベール・カミュ。アルジェリアでの極貧の幼少期、不治の病・結核との闘い、ナチスに蹂躙されたパリでのレジスタンス活動、幾多の女性とのロマンスー不条理な運命に反抗し続け、46年の生涯を駆け抜けたカミュの波瀾の生涯と作品、そして思想に迫る。」
これが、この本の表紙裏に書かれたうたい文句であり。
本の帯の裏には、コロナに翻弄された我々だからこそ振り返るべき、カミュの人生と作品「人間は死ぬ。これがこの世界の不条理のさいたるものです。人間は最初から罪もないのに死を宣告された死刑囚だと云うことです。それゆえ、幸福ではありえない。だとするならば、このいわば神から押しつけられた不条理をこえるような不条理を生きて、神をこえ、人間の条件をこえることに挑まねばならない。-本文より」とカミュの思想が要約されている。
カミュ伝は、面白かった。その理由は、彼の生い立ちと境遇が、貧困、幼少期に父を失い、しかも当時としては結核と云う不死の病の中、フランスの植民他であったアルジェリアを舞台に展開されたことで、その彼がその環境下で何を考え、どう生きたかにひきつけられたからである。
読み終わって、とくに印象に残った点は、サルトルの思想との違いであった。それは、作者のあとがきの次の文章に要約されている。「カミュは、しばしば、サルトルとならんで、実存主義の代表者とされてきましたが、サルトルが「実存主義はヒューマニズムである」と宣言したのと正反対にカミュは一貫してヒューマニズム(人間中心主義)の根源的な批判者でした。その意味でサルトルと論争して構造主義的な思考を提唱したレヴィ=ストロースなどの先駆者ともいえます。」私はかつて、人間中心主義が、今日の環境破壊をもたらした根底にあると持論を展開したことがあったので、この著者の視点には、深く共感するところがあり、実存主義が、ソ連邦崩壊以後の世界の中ですたれていった理由が、今日のリベラリズムの衰退とともにこのことと関係していると深く感じた。
今回のコロナパンデミックは、世界には、人間以外の存在があり、それへの対応を人間世界の論理だけで行おうとすれば、外出禁止令や都市封鎖と云ったファシズム的社会を招かざるをえないことを如実に示した。
中条 省平(Wikipedia)
概要
中条 省平(ちゅうじょう しょうへい、1954年11月23日 - )は、日本のフランス文学者、映画評論家・研究者。学習院大学文学部フランス語圏文化学科教授・同大学院人文科学研究科身体表象文化学専攻教授(兼任)。2025年3月退官、研究分野は19世紀のフランス小説(特に暗黒文学)だが、近現代の日本文学・ジャズ・映画・漫画などに造詣が深く、其々の研究・評論活動にも携わる。
麻布中学時代に「薔薇の葬列論」を執筆し、映画評論家・松本俊夫の目に止まり、中学生時代から評論家としての活動を始める。
東京大学大学院での指導教授は、フランス文学者・映画批評家でもある蓮實重彦。演劇評論家であり同僚でもあった佐伯隆幸(学習院大学名誉教授)とともに、学習院大学大学院人文科学研究科身体表象文化学専攻の設立を担い、初代専攻長に就任。その前身となった学習院大学表象研究プロジェクトを通じて、アニメーション映画監督として知られた高畑勲(元学習院大学表象研究プロジェクト特別研究員)、トリュフォー研究で知られる映画評論家・山田宏一などとの親交が深い。
略歴
神奈川県生まれ。父はマグロ船の元船長であった。麻布高等学校を経て東京外国語大学英米語学科に入学したが、講義に興味が持てず学業を放棄し3年間在籍の後に不登校が親に発覚して中退した。早稲田大学、上智大学、学習院大学、慶應義塾大学を受験して全て合格し、福永武彦、辻邦生、山崎庸一郎、白井健三郎、豊崎光一といった教授陣の豪華さに惹かれて学習院大学に入学、22歳にしてフランス語を始める。 1981年、学習院大学仏文科卒業。 1984年、フランス政府給費留学生としてパリに滞在。なぜか一人だけ日本寮生館ではなく、アメリカ寮生館に配された、などの逸話がある。 1987年、パリ第十大学第三期文学博士号を取得(専門は、暗黒文学)。 1988年、東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学、学習院大学文学部フランス文学科専任講師となる。近年は漫画評論にも力を入れており、「週刊文春」連載の漫画論「読んでから死ね! 現代必読マンガ101」では浦沢直樹、しりあがり寿、大島弓子、赤塚不二夫、安達哲、新井英樹、荒木飛呂彦、一條裕子、松本大洋、井上雄彦、古谷実、ねこぢる、皆川亮二らを解説した。2009年より手塚治虫文化賞選考委員。2025年3月学習院大学退官。
読後感
自分の問題意識にフィットしたこともあったか、珍しく一気に読むことが出来、すぐにも感想を書こうかとも思った。カミュの全貌が見えたと思ったからである。しかし、そのとき、まだ、カミュの作品を読んでいないことに気がついた。感想を書くのは、彼の不条理の三部作、「異邦人」「シーシュポスの神話」「ペスト」を読んでからにしようと思った。そこで平和堂での買い物のとき、スーパーの中の書店であまり期待せず探してみた。ところが偶然にも三冊共、各一冊ずつ残っていたので買い求め、読んでみることにした。
「異邦人」すぐに読み終えた。「ペスト」は時間がかかった。「シーシュポスの神話」は拾い読みした。小説の舞台がアルジェリアであることに驚いた。
しかし、小説については特に驚く感動はなかった。それは、神無きヨーロッパの人間を扱っていて、目新しいものが無かったせいかも知れない。ノーベル文学賞は、こうした人間像を現代の普遍的人間像として捉え、そこを描くことを評価しているように思える。カミュは、20世紀を指導した人間中心主義に異を唱え続けた点で西欧思想史の中では、異端であるが、草木国土悉皆成仏の東洋的日本的世界から見れば極当然の思想のように思える。しかし、近代ヨーロッパ思想の限界を示すものとしてみれば、ひび割れつつある西洋思想の矛盾を告発した初期の書として目新しいのかも知れない。
「シーシュポスの神話」抱えベレー帽をかぶってパイプをくゆらせていたS君は、カミュがそうであったように演劇の世界に飛び込んだが、上京し、雑誌の編集や演劇周辺の仕事でもカミュ的生活を続けていたが、大学を出て10年程経った頃、堅実で、賢そうな女性に出会うと一転して、放浪的生活から足を洗いまじめな雑誌の編集者となっていた。僕等の中の青春が終ったのは、その頃である。